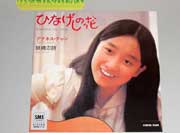VOL.173 * 2004/11/30
|
「地下鉄にのって」 猫
最近は騒音も低くなっているようですが、東京メトロが帝都高速度交通営団だったころは
走行中の車内では会話が困難でした。岡本おさみ作詞、吉田拓郎作曲の表題曲はそんな頃の
荻窪行き丸の内線の車内を描写しています。たぶん銀座で映画を観た帰りの若い二人は
まだそれほど親密でなく、ぎこちない会話がさらに地下鉄の音で邪魔されてしまいます。
ここからは想像ですが、下井草のアパートへ帰る男は新宿で降りるのでそれまでに
もうちょっと実のある会話をしたい。南阿佐ヶ谷が自宅の彼女はそんな気も知らず
つれない素振り。新宿御苑でも寄り道しようと言い出したかった男は歌の最後で…
「君ももちろん降りるんだろうね でも君はそのまま行ってもいいよ」なんだかだらしない。 |
VOL.172 * 2004/11/29
|
「想い出の小川」 フランク・プゥルセルOhc.
「ジェットストリーム 」が放送1万回を超えたそうで、すごいことです。 」が放送1万回を超えたそうで、すごいことです。
ラジオ番組では、永六輔とか小沢昭一とかウルトラ長寿番組けっこう有りますね。
ジェット・ストリームを良く聞いていたのは学生時代です。四畳半の万年床で
「ロンドンは今○時、ウエストエンドでは…」などと聞くのも悪い気はしませんでした。
ただ、いつの間にか寝てしまうことも多く気がつけば放送時間終了前の番組
「ミッドナイトメロディ」のテーマ曲だったこともしばしばです。たぶん
FM大阪のローカル番組だったでしょうが、「ミスターロンリー」と同じ
プゥルセルのしゃれた演奏でアダモの佳曲が流れ夢心地にさせてくれました。 |
VOL.171 * 2004/11/28
|

[日曜日」 高田渡
電話やメールをなんとなく遠ざけて、逢いたい人の来そうな場所に
偶然の出会いを求めて足を運ぶ。そんなことを思う若者って今でも
居るんでしょうか。いや、ストーカーとは違います。決して待ち伏せしたり
後をつけたりはしません。自分と、逢いたい人どちらにとっても必然性の
ありそうな場所を選んで、幸運な邂逅(かいこう)を待つだけです。もしも、
本当にふさわしい場所だったら二人が出会うことも、一人で待ちぼうけ
することにも同じような価値があるのです。日曜日の喫茶店で
高田渡は彼女に恋することをあきらめ、彼女の街に恋をしました。 |
VOL.170 * 2004/11/27
|
「ボーイッシュベイビー」 山口百恵
「秋桜」や「さよならの向こう側」などスローな歌唱の山口百恵からは
想像しがたい、テンポのいいリズミカルなナンバーです。
ただしビートだけの曲では決してなく、聞き手に声とメロディがしっかり
印象づけられる点が並みの歌手じゃないところでしょう。
しいて表現するなら、上体は激しくテンポをリードしながらも
二本の足はしっかり地について、先を見通しているような安心感を
かもし出しているのです。1977年のトータルアルバム「百恵白書」に収録。
もちろん阿木燿子 宇崎竜童の作です。 |
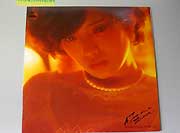
「A Face in a Vision」山口百恵アルバム |
VOL.169 * 2004/11/26
|
「ディスクッドビーザスタートオブサムシング」 グラント・グリーン
北風が吹こうが、雲がたれこめていようがこんなグルーヴィな演奏を
聴けばウキウキとコートをはおって出かけたくなります。
ジャズギター奏者の中では比較的地味な存在のグラント・グリーンですが
1965年にブルーノートから出たアルバム「I Want to Hold Your Hand」では、
まさしくスタート・オブ・サムシングを手に入れたと感じさせる
軽快なメロディーラインでコンボをリードしていきます。そしてバックで
ささえるラリー・ヤングのオルガンとエルビン・ジョーンズのドラムスもイイ.。
演奏者の自然な善意が聴いている側にも伝わってくる幸福な演奏です。 |
VOL.168 * 2004/11/25
|
「落日のテーマ」 五輪真弓
この人のデビュー曲「少女」に、縁側好きな少年だった私は惹き付けられました。
ヒットする前に歌詞を書き写し、自分でコードをさぐって弾き語りを試みたりしていました。
やがて大学生活に入り、最初の夏休みに帰省したときにNHK銀河TV小説という
夜9時台の帯ドラマで石川達三の「僕たちの失敗」を見ました。そのテーマ曲が
彼女の自作自演による表題曲だったのです。「どこまでも 果てをしらない…」で
始まる、けだるくも美しい旋律は当時のドラマの音楽としては抜きん出て
新鮮かつ感動的でした。私と同世代の皆様でいまだに、空の谷間にこだまする
落日のテーマを時々心に響かせるかたもいらっしゃると思います。 |
VOL.167 * 2004/11/24
|
「悲しき初恋」 パートリッジ・ファミリー
1970年頃のティーンエイジ向けのポップス、いわゆるバブルガム
ミュージックの伝播力というのは結構たいしたものでした。
欧米のヒットチャートのナンバーが程無くして、日本の田舎の中学生の
心を少なからず揺さぶったりしていました。ひとつひとつの楽曲の
芸術性という見方では、いささか稚拙なレベルかも知れませんが、
どの曲にも必ずひとつかふたつ光る部分があって捨てがたいのです。
表題曲はデビット・キャシディというアイドルを中心とした企画ユニットですが
アレンジが素晴らしく、ちょっとせつない前奏や間奏が好きでした。 |
VOL.166 * 2004/11/23
|
「二 人」 赤い鳥
山上路夫 村井邦彦コンビのような作風ですが調べてみると
大川茂 山本俊彦というメンバー自作でした。のちに分裂するグループ名
でいうと、紙ふうせんでなくハイファイセットのほうですね。
高校生の私はこの曲の出た頃の労音の赤い鳥コンサートに出かけています。
めあては紅二点の御姉さま平山泰代さん、新居(のちの山本)潤子さん。
お二人ともきれいでしたが、解散後の様子を考えるとこの頃から
あまり仲は良くなかったのでしょうか。でも、そんな事を感じさせない美しい曲です。
♪夜明け前のひとときの とても悲しいほどの静けさを… あなたの大事な人がいつか忘れている時に。 |
VOL.165 * 2004/11/22
|
「私のものはあなたのもの」 サリナ・ジョーンズ
サリナ・ジョーンズのデビューアルバム「アローン&トゥゲザー」を
はじめて聞いたのが何年ごろだったかさだかに思い出せません。
場所はジャズ喫茶、当時はどこでも演奏中のレコードジャケットを
見やすい場所に掲げてくれていました(今も掲げてはいるのでしょうが
CDの場合は残念ながら見難い)。ジャケットの全身写真からにっこり
ほほえむサリナの笑顔と、ビリー・ホリデイの流れをくむ暖かい歌声に
魅せられました。表題曲 Everything I Have is Yours は、しっとりとしたバラード
ですが邦題はざっくばらん過ぎ。「我がすべてを君に」くらいでどうか。 |
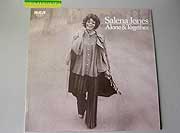
「アローン&トゥゲザー」サリナ・ジョーンズ LP |
VOL.164 * 2004/11/21
|
「たそがれの御堂筋」 坂本スミ子
学生時代にかなり関西文化に同化したわが身を、びりっと引きはがして
九州で社会人を始めた私は福岡から宮崎と、だんだんドメスティックな世界に
戻っていきました。それなりの暮らしやすさもある反面、いちまつの寂しさも
あったのでしょう。何かの拍子に「やっぱ大阪 好っきゃねん」という
内心がむくむくと顔をもたげました。表題曲がラジオから流れ出したのは
仕事帰りの車の中だったと思います。「みどおすじーの たーそーがれは…」
予想しないときに思いもしない音楽がピタッとツボに嵌る効果はラジオならでは。
都会、夕陽、年上のヒト、いろんな要素の想起がからまって涙にくれました。 |
VOL.163 * 2004/11/20
|
「アイフィールファイン」 ビートルズ
私がティーンエイジだった1970年を中心とする時代がステレオという
概念がもっとも脚光をあびた頃で、NHKラジオが第一と第二放送でそれぞれ
左右チャンネルの音を同時に放送するクラシック番組をやったステレオ原始時代から
FMステレオ放送の開始、さらに前後左右4チャンネルの再生装置やレコードが普及して
すぐに下火になったりとめまぐるしい10年でした。ビートルズでいえば自前のレーベル
「アップル」創立の1968年頃がモノラルとステレオの切り替わる時期だったでしょうか。
やがて以前のモノラル時代のヒット曲もステレオで再発されますが機械的なステレオ化
による違和感もそれはそれで妙になつかしく、較べて聴き直してみたりもします。 |

ザ・ビートルズ コンパクトLP |

あの頃の全日空トライスター(伊丹) |
VOL.162 * 2004/11/19
|
「さようならの彼方へ」 内山田洋とクール・ファイブ
私の好きな純歌謡曲のベストアルバムを作るとするなら必ず入る曲です。
この曲が出た1978年に私はモラトリアムのプータローにケリをつけ、
九州では大手だった流通企業に就職を決め、赴任地の福岡へと向かいました。
伊丹の空港からギターケースをかかえて乗り込んだ全日空のトライスター、
窓から見下ろす池田から能勢にかけての山々は色づきかけていました。
「夜の国際線で ただひとり旅立つの…」昼なのにおもわず口ずさんだのは
企業人になるというステイタスの変化が、異国へ旅立つ気分だったのでしょう。
千家和也・筒美京平の作、前川の歌に増してバックの淡々としたコーラスがなかせます。 |
VOL.161 * 2004/11/18
|
「素敵なあなた」 アンドリュース・シスターズ
大学に入ってしばらくしたころアルバイト代をためてセミ・アコースティックの
エレキギターを買いました。独学で「ジャズギターもどき」を練習しましたが
数少ない最後まで弾ける曲が表題曲 Bei Mir Bist Du Schön でした。
シンプルなコード進行のお陰でヴァースからコーラス、さらに「アドリブもどき」
までつけて悦に入っていましたが結局このレベルより上に行くことはありませんでした。
アンドリュース・シスターズのヴォーカルはドイツ語まじりの歌詞がリズムよく乗って
気分が浮き立ちます。レコード時代にはもっと色んな演奏者のものがありましたが
CDを探すと意外に少ない、ちなみに「バックシャン」も死語ですね。 |
VOL.160 * 2004/11/17
|
「昨日のような出来事」 麻田浩
ソニーミュージックショップ内での、この人の紹介では「森山良子、マイク真木と
並び日本のフォークの草分け的存在」となっていますが、ラジオ番組などで
日本フォークの歴史が紹介されるときに麻田浩の曲がかかる事はまれです。
1970年代初期にカントリー調のフォークでさわやかな風がひととき吹いた記憶、
少しだけ残っていました。そういえばこんな季節、風邪をひくと表題曲の二番、
「冬になると決まってカゼをひき バカはカゼをひかないのねと おまえは フトンの中で
笑ってたけど オレも カゼをひいたぜ今年の冬は」この一節を口ずさんでいました。
♪あれーからー もうすでに 30年も たったのに まるで 昨日のようだよ… |
VOL.159 * 2004/11/16
|
「ヘイ・ポーラ」 ポールとポーラ
ティーンエイジの少年と少女が、結婚したいの卒業まで待てないのと、
結構あけすけに歌い掛け合います。ローティーンの私にとって
USAのニーチャンネーチャンの話とはいっても微妙に
穏やかならない雰囲気をかきたてられた事を覚えています。
でも、サビの True love means planning a life for two 以降のメロディが
あまりに美しく、コーラスもアレンジも素敵だったので
邪念は消され、輸入品の高級菓子のパッケージを見るような
ささやかな憧れへと昇華していったのでした。 |
VOL.158 * 2004/11/15
|
「のすたるぢや」 布施
明
1980年代に出ていた曲と思い込んでいたのですが、去年の今頃だったんですね。
FMからとったテープに古井戸の「ステーションホテル」なんかと一緒に
入っていたものでそんな気がしました。調べてみるとオリジナル・ラブの
田島貴男の曲ということですが、ノスタルジックでエキゾチックな曲そのものについて
詳しい情報はわかりません。歌詞から察するに、外国へ転居することに
なった少年が学校の友達に見送られて故郷の町を出る列車に乗ったところ、
という情況のようです。夢想的なリアリティを秘めた布施の歌い方
オジサンはこういうの大好きです。 |
VOL.157 * 2004/11/14
|
「パーリースペンサーの日々」 レイモンルフェーブル Ohc
私の通っていた中学校で、たぶん下校時間の合図か何かで
生徒会の係が音楽を流していたと思います。或る日、
暗くなりかけていた校舎の庭にこの曲が鳴り響きました。
何か急を告げるようなメロディと、カッコいいオーケストレーション。
内心こんな良い曲しらなかったと思いながらも友達の生徒会長に会った時は
くやしくて言いませんでした。放送室でレコードを手にとって見てわかりました。
当時大ヒットした「シバの女王」のB面だったのです。偶然手に入れた
曲だったんだと自分を納得させ、ささやかな嫉妬をおさめたのでした。 |
VOL.156 * 2004/11/13
|
「私を静かな草原に埋めて」 ユリ・珠美
おだやかで良い曲ですが、思ったよりもマニアックなナンバーとなっていました。
CD化されていないのみならず、歌手や使用TV番組に関しても
検索できる資料がほとんど残っていません。フォーク調の歌詞で
「私を静かな草原にうずめて ましろな花が いつも咲いている」という出だし、サビは
「あなたに愛されて許された日々を…」。中年世代でピンと来た方もいらっしゃるはずです。
1970年にTBS系の月・金昼の帯ドラマ「愛の劇場2」として放映された
島かおり主演の作品「愛と死と」のテーマソングなのですね。(目黒みずえ作詞)
放送時間が午後1時なので夏休みにでも見たのか、曲はしっかり覚えています。 |
VOL.155 * 2004/11/12
|
「雨のフィーリング」 フォーチュンズ
12月の雨にくらべると11月の雨は冷たさも華やかさも中途半端な感じ、
そんな11月の雨にぴったりな曲というとこれじゃないでしょうか。
1971年に地味にヒットしたイギリスのソフトロックを久しぶりに思い出しました。
エジソンライトハウスの「恋の炎」などで有名なトニー・マコーレイの作、
歌っているフォーチュンズは60年代から活躍しているコーラスグループです。
確かに70年代ニューロックの味も加わっているのですが、
リバプールサウンドのスーツに細身ネクタイ姿の雰囲気も色濃く残っており、
懐かしい暖かみを残した11月の雨にふさわしいサウンドです。 |
VOL.154 * 2004/11/11
|
「どうしてこんなに悲しいんだろう」 よしだたくろう
「風のなかを ひとり歩けば 枯葉が肩でささやくよ」 これも高校時代の
記憶を呼び覚ます曲です。吉田拓郎ごく初期のフォーク村手造り工房的作品が
LP2、3枚在ったあと、「結婚しようよ」を含むメジャー色の濃くなったこの
アルバム「人間なんて」がでました。今の時代に聴けば出来のばらつきのある
作品が混在した、まとまりのない感じがあるかもしれません。
当時の我々は、友達のアパートの屋上で「人間なんて」や「川の流れの如く」なんかを
ヘビーゲージのギターをかき鳴らしながら大声で歌ったあと、
ひとり家に帰って表題曲をちょっと小声で歌う、絶妙のマッチングを楽しんでいました。 |
VOL.153 * 2004/11/10
|
「詩人の魂」 ジュリエット・グレコ
高校生の頃1,100円の廉価ベスト盤を買って初めて聴いたシャンソンの名曲、
「ラ・メール」なども作っているシャルル・トレネの作詞作曲です。
ぞくっとするような出だしからなめらかに高音へと昇っていく冒頭部分で
すっかり惹き付けられてしまいました。同じレコードに入っていた
「枯葉」も、もちろん良かったけれど文学に目覚めたばかりの
少年にとっては詩人の魂というタイトルも魅力的で気に入りました。
詩人が亡くなっても、歌は残り街角にいつまでも流れる、そんな意味がこめられています。 |
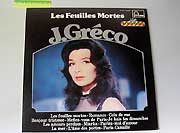
「ジュリエット・グレコ」フォンタナ ベスト盤 |
VOL.152 * 2004/11/09
|
「暗い港のブルース」 キングトーンズ
キングトーンズといえば「グッドナイトベイビー」の一発ヒットのグループと
誤解している向きはまだ良いほうで、名前も知らない世代も増えてきていることは
残念です。彼らは1960年代から活躍している日本の正統的なドゥ・ワップスタイルの
コーラスグループで、内田正人のファルセットボーカルとアカペラコーラスの絶妙の
組み合わせは、シャネルズもゴスペラーズも目じゃないぜと、オジサンはつぶやきます。
表題曲はアマリア・ロドリゲスの有名なファドとは直接関係ありませんが、
なかにし礼の詞には遠い異国への思いを暗示するせつなさが在ります。
彼らよりも演歌色の強いコーラスグループの方が売れてしまったのは時代が早すぎたのでしょうか。 |
VOL.151 * 2004/11/08
|
「コートにすみれを」 ジョン・コルトレーン
1957年にプレスティッジレーベルから出たアルバム「コルトレーン」に収録。
バックはマイルス・デイビスクインテットのリズム隊を中心にしたメンバーです。
表題曲はマット・デニスやフランク・シナトラで有名なバラードですが、
コルトレーンはボーカルに勝るとも劣らぬ表現力でテナーサックスを歌わせます。
この当時コルトレーンはおよそ30歳ですが、この演奏を聴いていると、
ずっと年上の男の優しさと年相応の活力をあわせ持っていたように感じさせます。
主体的な表現と素早い協調の求められるジャズメンの生き方がもたらしたものかも知れません。 |
VOL.150 * 2004/11/07
|
「シャインオンミー」 アグネス・チャン
アグネス・チャンという人は「ひなげしの花」の可憐な少女の姿から、
多言語を駆使する活動的な知識人、さらに大人の歌手まで幅広い顔を持っています。
私が特に好きなのは1978年から80年頃のカムバック直後の曲たちです。
当時社会人になりたての少々緊張の強い日々をいやすのに好適だった
AOR系の洋楽ヒットや渡辺真知子、太田裕美そしてアグネスなどをカセットテープに入れて
車の中で何度も聞きました。表題曲はバックのシンセオルガンのコードが耳に心地よく、
励ましてくれるような彼女の声がなんとも親しみ深く感じられました。
1980年11月のシングル曲ですが、現在市販CDでは収録がないようです。
2014年にベスト盤でCD化されました |
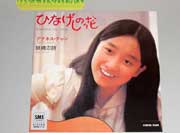
「ひなげしの花」 アグネス・チャン シングル盤 |
VOL.149 * 2004/11/06
|
「君を想いて」 ビリー・ホリデイ
たまたまTVで出会った映画、1993年メル・ギブソン主演の「時を越えた告白」。
見るつもりじゃなかったのに最後までみてしまいました。
人工冬眠実験を経て再会する最愛の人という、映画だから許される
ギリギリの無理設定でしたがB-25爆撃機の飛行シーンや子役がよく
出来ていたので、けっこう楽しめました。そして何よりも効果的に使われている
挿入歌 "The Very Thought of You"の甘い言葉とメロディが思いに残ります。
ビリー・ホリデイのジャジーな歌唱が白人の若い二人の生活に
自然にフィットしている様子は、まさに古きよき時代ですね。 |
VOL.148 * 2004/11/05
|
「いたずら書き」 あべ静江
街路樹がちらほら色づく頃になるとこんなしっとりとした曲が甦ります。
1976年に財津和夫の作詞作曲、乾裕樹編曲で発表されました。
マルチトラックのひとりコーラスがポイントの曲なのでTVの歌番組向きでは
なかったのですが、言葉になっている部分と秘めた内心の二面性が効果的に
表現されているのでレコードで聞くと聴き応えがあります。
さらに、レターメンの「ビコーズ」を想わせるストリングスの間奏後に
キーが半音上がった最後のコーラスは3声のアレンジになり、盛り上がりが絶品です。
「・・・今歩いてる道を行きます 昔の日々に戻りたいんじゃないんです これは私のただのいたずら書き。」 |

「コーヒーショップで」 あべ静江 シングル盤 |
VOL.147 * 2004/11/04
|
「クリフハンガー」 トレバー・ジョーンズ
1993年のスタローン主演の山岳サスペンス映画、4000m標高の山中で不時着した
犯罪組織の小型ジェット機と積荷の略奪した現金をめぐり、目もくらむような断崖で
死闘が繰り広げられる…という内容は聞いていましたが私はまだ見ていません。
テーマ音楽を何度か耳にした程度であえて取り上げるのは、昨日からの米大統領選
の様子にあまりにぴったりだからです。一夜明けた3日早朝のCNNサイトの見出しに
CLIFFHANGER IN OHIOと、でかでかと出ていて思わず「うまい」と思いました。
さらに、単に絶体絶命の状況を連想させるだけでなく、Wikipediaによれば
中途半端で後味が悪い最終回を迎える米国TVドラマをこう呼ぶようです。 |
VOL.146 * 2004/11/03
|
「マイホームタウン」 熊倉一雄ほか
1970年代初期のカウンターカルチャーの風はラジオの深夜放送ばかりでなく、
従来は少年向けのメディア、例えば「少年サンデー」そしてNHKの連続人形劇
といったところにも吹いてハイティーンや大人の愛好者をひきつけました。
井上ひさし、山元護久作の「ひょっこりひょうたん島」をさらに先鋭化した人形劇
「ネコジャラ市の11人」は、高校に入って色んなことに目覚め、家のTVも
カラーになった頃だったので思い出深いものがあります。当時所属していた
学校の放送部でも皆が触発され、世に出て間もないオープンリールのソニーVTRを使い
白黒の短編ながらも人形劇番組を制作したのは1973年のことでした。 |
VOL.145 * 2004/11/02
|
「夢見る頃を過ぎても」 ハリー・アレン
こちらは古いスタンダード。「朝日の如くさわやかに」などで有名な
ロンバーグ=ハマーシュタイン2世のコンビによるものです。
特に美味しいメロディがあるわけでもないシンプルなワルツですが、
「マイ・フェバレット・シングス」のコルトレーンの例にみられるように
モダンジャズの素材としては料理のやり甲斐のある素材だったようです。
白人テナー奏者アレンによる演奏は2000年のリリースですが泣かせる料理です。
When I grow too old to dream, I'll have you to remember. |
VOL.144 * 2004/11/01
|
「夢みる頃」 伊藤咲子
山口百恵世代のアイドルポップス歌手の中で、ぱっと「ひまわり」のように咲いて
「乙女のワルツ」でピークに登り、いつのまにか消えてしまった印象の伊藤咲子。
くわしいことは分かりませんが後半は楽曲やスタッフに恵まれなかった感じです。
表題曲はデビュー2作目のシングルでひまわり娘と同じ阿久悠作詞、シュキ・レヴィ作曲。
この作曲者がなんだか謎なのですがメロディ、特にサビの部分が魅力的です。
15、6歳の少女としてはしっかりした質感の声で裏声の伸び方が心地よいので
今の時代でもプッシュすれば新しいファンをつかめそうな気もします。 |

「乙女のワルツ」伊藤咲子 シングル盤 |
■ 前月分のページへ ■
△Click△
Mail to:
handon@rs-kumamoto.com
」が放送1万回を超えたそうで、すごいことです。